
|
|
「メビウスの輪」1小説「メビウスの輪」1 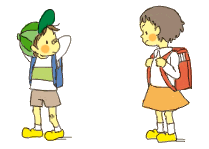 俺の名は信吾。 幼いころから、父の暴力と母の言葉に傷つけられてきた。 小学校時代、珍しく家族そろってレストランに行ったとき、 大好きなエビフライを最後に楽しみに取っておいた。 他のものを食べて、さあ食べようとフォークを刺す瞬間、 横から別のフォークが出てきて、食べられてしまった。 目の前から消えたエビフライに呆然としたが、 その手が父の手だと分かり、諦めてしまったのだ。 悠然と俺に見せびらかすかのように エビフライをゆっくり美味しそうにほおばる父。 「好きなものや大事なものは、先に延ばすと ルールが変わったりして、手に入らなくなったりする。 だから優先順位をつけて片付けなくてはいけないのだ。」 偉そうに説教を垂れる父。ただ食べたいだけじゃないか。 子供のものを横取りするなんてひどすぎる。 そう思いながらも、何も言えなかった。 うちでも、もたもた食べてると、 台所に下げられてしまう。 ゆっくり味わう余裕などないのだ。 アニメの「巨人の星」よろしく、 ちゃぶ台をひっくり返されたこともある。 文句を言おうものなら、母でも子供でも張り倒される。 誰も父には逆らえないのだ。 母はその鬱憤をはらすかのごとく、 子供達に当り散らす。 特に俺には「あんたを産んだからこんな弱い体になっちゃったのよ。 あんたなんか産まなければ良かった。」とまで、のたまう。 俺はこんな両親の元に生まれたことを恨みながらも、 表面上は親に敬語を使ってまで、優等生を演じてきた。 大学に入って、アルバイトでもらったお金を一部家計に入れるまで 食べさせてもらってるという負い目を感じさせられてきたのだ。 うちでいい子の代わりに、 学校では隠れて弱いものいじめをしたりしてきた。 自分の鬱憤をどこにはらしていいか分からなかったのだ。 父は酒を飲むと、誰かれかまわず暴力を振るっていたが、 機嫌のいいときは、なぜか姉だけ可愛がっていた。 それも気に食わなかった。 母も姉を相談相手として頼りにしてたし、 誰も俺を必要としていなかった。 認められようと必死に勉強やスポーツをしても、 性格や生活態度がひねくれてると言われ、 ますます依怙地になってしまうのだ。 そんな俺を唯一認めてくれた奴がいた。 母や姉を見て、女に嫌気がさしてたのに、 そいつにだけは素直になってしまうのだ。 彼女とは同じ大学で出会った。 それまでテニスなど、スポーツの部活しかやってこなかったのに、 新入部員勧誘のとき、彼女に勧められて 合唱サークルに入った。 なぜか断れなかったのだ。 彼女の名は幸恵。 名前とは反対に幸薄そうなひっそりした山野草の感じだ。 そのくせ、妙に説得力があった。 「心にわだかまってるものを歌で吐き出してみませんか?」 そう言われて、「そんなこと本当に出来るのか?」 と興味を示してしまったのだ。 よっぽどストレスがたまっていたんだろう。 彼女の癒しの雰囲気に呑まれたということもある。 そのまま新入部員勧誘コンパに連れて行かれ、 酒を初めて飲み、吐いてしまった。 介抱してくれたのも彼女だった。 居酒屋の男女兼用のトイレに付いてきて、 吐く俺の背中を優しく撫で続けてくれた。 「大丈夫?初めてだったのね。」 その言葉にドキッとしたが、 酒や吐いたことだと気づき、赤くなってしまった。 「飲んだことくらいあるさ」 わざと毒づいてみたが、お見通しのようだった。 「私も初めて飲んだら、気持ち悪くなっちゃったの。 だから苦しさが分かるんだ。」 幸恵は1年先輩で、去年自分も吐いたらしい。 ふらふらしながら、席に戻ったが、 つい視線が彼女の方に向いてしまう。 他の先輩と話してる彼女が、 心配そうに俺をチラッと見る。 目をそらしても、追ってきて「モナリザ」みたいだ。 注意してるくせに、なぜか優しいまなざしで見つめる。 「もうこれ以上飲んだらだめよ。」 そう言って、俺のためにウーロン茶を頼んでくれた。 高校時代だって、もてなかったわけじゃない。 女に優しくされたこともあったのに、 こんなに胸に沁みなかった。 言い寄ってくる女を相手にしたことはあっても、 自分から好きになったことはなかった。 女を警戒していたせいもある。 母や姉は、父の暴力が 次第に俺一人へ集中してきても、 自分達に災いがふりかからないように 見て見ぬ振りをした。 そんな卑怯な女が嫌いだった。 弱いのは分かってる。 でも、たとえ後で「大丈夫?」と言われても 許せなかった。 もちろん返事もしなかったが。 だから、彼女の優しさが不思議だった。 見返りを求めないような感じがして、 素直に受け入れられるのだ。 最初は怖かった。 卵の殻のように、一箇所でも割れれば、 崩れ落ちてしまいそうな自分の殻。 人に弱みを見せてしまったら、 もう立ってること自体出来なくなってしまう。 そんな恐怖感があって、 心を開くことが出来なかったのだ。 そんな頑なな心を静かに溶かすような 温かさが幸恵にはあった。 後で知ったことだが、彼女自身もまた 家庭で傷つきながら育ったらしい。 アダルトチルドレン特有の 傷つきたくないがための優しさなのかもしれないが。  私の名は幸恵。 「幸に恵まれる」のではなく、 「自分は幸いで恵まれてる」と思えるようにと願って こう名づけたそうだ。 でも、私はそうは思えない。 傍目には幸せに見えるかもしれないが、 自分では実感できないのだ。 カールブッセの詩「山のあなた」ではないけど。 「山のあなたの空とおく 幸い住むと人の言う。 ああ、われ人ととめ行きて 涙さしぐみ かえりきぬ。 山のあなたになお遠く 幸い住むと 人の言う。」 (上田敏 訳) 私の家庭は経済的には恵まれていたが、 精神的には満たされないものがあった。 両親の不仲と、子供への愛情不足。 父も母も幸福を外に求めて、 子供を顧みなかった。 私は別な意味で父に愛されてはいたが、 その愛?は受け入れがたいものだった。 小さいころ、寝室に父がお休みを言いにくる。 額にキスするまではいい。 それが段々エスカレートしていったのだ。 口に出すのもおぞましい。 ただ身を硬くして、嵐が去るのを待つしかなかった。 記憶もおぼろげで、現実だったのかさえ分からない。 ただ、あまりの恐怖に声も出なかった私が、 必死に身をよじり、ベッドから落ちた音を聞きつけて、 母が私の名を呼んだとき、父も我に返ったのか、 それ以来、寝室に来なくなった。 そして、家庭にも戻らなくなっていった。 母は気づいていたのかどうか分からないが、 父にも私にもよそよそしかった。 そして、買い物で欲求不満を晴らすしていたのか カードでブランド物を買いあさっていた。 まるで、愛情ではなくお金しか与えない父へ 思い知らせるかのように。 そして、最後には若い男性まで買っていた。 お金さえあれば、幸せが買えるとばかり 浪費していたけど、幸せそうには見えなかった。 美人なくせに笑わない。たとえ笑っても、 口元をゆがめるだけで、目元は笑ってないだけに、 不気味ささえ感じてしまう。  その母に、なぜか似なかった私。 でも、私はお金も美貌も要らない。 ただ、優しい家庭が欲しかった。 もう両親には何も望まないが、 私は愛する人と可愛い子供の居る 幸せな家庭が作りたい。 お金なんて無くたって、 私も働いて、一緒に生活さえ出来ればいい。 そんなふうに願っていた。 彼と会ったのは、 その夢を切実に思い始めたころだった。 大学の合唱サークルに私が勧誘した たった一人の新入部員。 他の部員は何人もの新入部員を捕まえて、 誇らしげにしていたが、 地味な私には、誰も立ち止まらないし、 たとえ止まっても、話を聞いてくれない。 そんなとき、彼と出会ったのだ。 筋肉質で硬派の彼は、いかにも体育会系で 合唱などやりそうには見えなかった。 でも、なぜか心が疲れてるように思えたのだ。 だから、駄目でもともと、 「心にわだかまってるものを歌で吐き出してみませんか?」 と声をかけてみた。 彼はハッとしたように立ち止まり、 「そんなこと本当に出来るのか?」 と関心を示してくれたのだ。 案の定、彼はテニスなどやってて、 合唱は未経験、興味もなかったが、 なぜか新入生歓迎コンパについてきた。 どうせ「タダ酒が飲める」と踏んだのだろうと危ぶんだが、 そうではなかったらしい。 お酒は初めてで、吐いてしまったのだ。 勧誘した責任も感じて、私は必死で介抱した。 トイレで吐く彼の背中もさすり続けた。 私自身、去年同じ思いをしてるだけに、 辛さが身に沁みて分かるのだ。 でも、それだけではないかもしれない。 彼のまっすぐ見つめる目が怖いほどだ。 でも、その視線に気づいて、 目をそらそうとすると、 彼のほうが先にそらしてしまう。 だからかえって追ってしまうのだ。 年下の男の子に何を考えているんだと、 自分に言い聞かせた。 年下にかかわらず、男性には恐怖を感じていたが。 父とのことがトラウマになってるのか、 今までもうまく男性と付き合えなかった。 こんな私でも申し込んでくれる人は居た。 でも、キスさえ拒否する私に 「美人でもないくせにお高くとまってる」などと言われ、 もう付き合うこと自体イヤになっていたのだ。 でも、彼はそんな私を見透かすように 少しずつ、近づいてきた。 ハリネズミの距離を保ちながら。 私が遠のけば、それ以上近寄らない。 そのくせ、私が恐る恐る近づいても 拒否しないで受け入れてくれるのだ。 親に受け入れられたことのない私にとって、 そんな体験は初めてだった。 今まで逢った男性は、性急に求めて、 得られないと分かると、さっさと去っていった。 受け入れてくれるどころか、 「自分を受け入れてくれない!」と苛立ちを隠さない。 友達で居るうちはいいのだけど、 それ以上の愛情を求めたら、 見返りも求められる。 それを与えられない私は、 いつまでたっても恋人にはなれないのだ。 彼も傷を持ってるようだった。 だからその傷口に触れないよう 労わってくれるのだ。 しばらくはこの状態が続いてもいいかな。 友達以上、恋人未満なんて中途半端だけど。 続き |